このイベントは終了しました
2025年7月18日(金) ・ 19日(土)
No.488 サンシティ名画劇場「関心領域」
第96回アカデミー賞国際長編映画賞受賞。1945年、アウシュビッツ収容所の隣で幸せに暮らす家族がいた。しかし、壁ひとつ隔てたアウシュビッツ収容所の存在が、音、黒い煙、家族の会話や視線、そして気配から着実に伝わってくる。その時に観客が感じるのは恐怖か?不安か?それとも無関心か?最大の衝撃作にして、最大の問題作があなたに問いかける。
イベント詳細情報

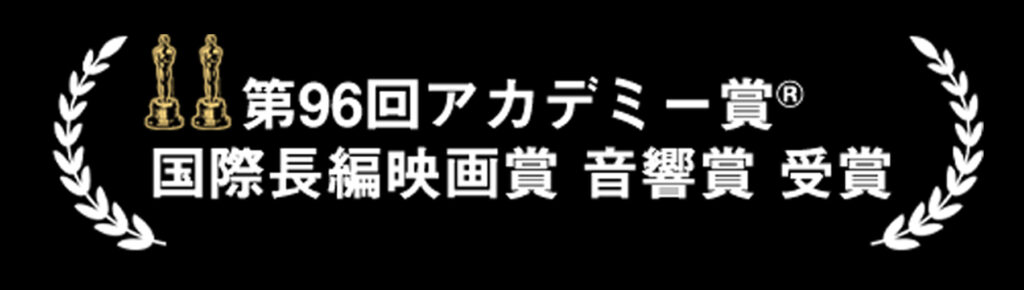



空は青く、誰もが笑顔で、子どもたちの楽しげな声が聞こえてくる。そして、窓から見える壁の向こうでは大きな建物から煙があがっている。時は1945年、アウシュビッツ収容所の隣で幸せに暮らす家族がいた。第76回カンヌ国際映画祭でグランプリに輝き、英国アカデミー賞、ロサンゼルス映画批評家協会賞、トロント映画批評家協会賞など世界の映画祭を席巻。そして第96回アカデミー賞で国際長編映画賞・音響賞の2部門を受賞した衝撃作がついに日本で解禁。
マーティン・エイミスの同名小説を、『アンダー・ザ・スキン 種の捕食』で映画ファンを唸らせた英国の鬼才ジョナサン・グレイザー監督が映画化。スクリーンに映し出されるのは、どこにでもある穏やかな日常。しかし、壁ひとつ隔てたアウシュビッツ収容所の存在が、音、建物からあがる煙、家族の交わすなにげない会話や視線、そして気配から着実に伝わってくる。その時に観客が感じるのは恐怖か、不安か、それとも無関心か?
壁を隔てたふたつの世界にどんな違いがあるのか?平和に暮らす家族と彼らにはどんな違いがあるのか?そして、あなたと彼らの違いは?

-1024x724.jpg)
PRODUCTION NOTE
残虐行為の副産物的な犠牲のひとつは、言語表現そのものかもしれない。言語はねじ曲げられ、真意を剥ぎ取られ、そして血の通わない貧弱な婉曲的な表現に作り替えられる。「最終的解決」ほど有名で――悪名高く――はないものの、ポーランドのオシフィエンチム郊外にあるアウシュヴィッツ強制収容所群を取り囲む40平方キロメートルの地域を表現するためにナチス親衛隊が使った「関心地域(The Zone of Interest)」(ドイツ語ではinteressengebiet)も同じように徹底して細やかで曖昧がゆえに不安を抱かせる言葉だ。
2014 年、作家のマーティン・エイミスは、協力者、加害者、収容者で視点が代わる恐ろしいピカレスク小説のタイトルに、この表現を採用した。この小説の中で、ある登場人物は、この「区域(zone)」は、自分の素顔を映し出す鏡のようなものだと表現している。長年、映画化の構想を練ってきたジョナサン・グレイザーの映画は己の姿を見ることを断固として拒否する人間を描いた映画である。気づき、分かることで自分たちが狂ってしまうことすらあるのだ。
グレイザーが注目するのはアウシュヴィッツ・エリアでの一般市民側の生活にある。彼は裕福で出世欲の強い強制収容所の所長であるルドルフ(クリスティアン・フリーデル)を家長に持つ一家に対する、手の込んだはっきりとした嫌悪へと観客をいざなう。贅沢な補助金を得て入居しているヘス家の2階建て、漆喰作りの邸宅には、牧歌的なアーリア人の牧歌的な白昼夢とその上に――文字通り――築かれた悪夢のような現実が共存している。
明日は彼らの手にある。ルドルフの妻ヘートヴィヒ(ザンドラ・ヒュラー)は、訪ねてきた年老いた母親と最近の造園の取り組みについて雑談の中で、邸宅の広大な裏庭むき出しのレンガの壁をツタで覆い、やがてツタが伸びて境界線を完全に見えなくする予定だと説明する。「ユダヤ人は壁の向こうにいる」と彼女は付け加えたが、この真実には最も恐ろしい種類の存在の否定が隠されている。収容所は死の暗雲が立ち込める――これをエリ・ヴィーゼルが「静かな青空の下に広がる煙のかたまり」と表現した――が立ち込める中、この偽りのエデンの園で、ヘスたちは普通の暮らしを送ろうと努力する。
長年、グレイザーは強烈で、むき出しの恐怖を描いた作品を監督してきた。彼がアウシュヴィッツを題材にした場合も限界まで押し進めると思うだろうが、予想を裏切る手法が使われた。歴史上の残虐行為の表現は、アラン・レネからスティーヴン・スピルバーグ、クエンティン・タランティーノに至るまで映画監督たちが取り組んできた複雑な題材であるが、グレイザーは大胆にも真逆からの方法論を選択した。綿密に調査された歴史的資料に基づき、そしてエイミスの小説の物語を大胆に再構築することで、現代のホロコースト映画の歴史に画期的な作品を作り上げた。
2013 年の映画「アンダー・ザ・スキン 種の捕食」の中でグレイザーは、無慈悲でありながら無邪気でピュアな心を持つ地球外生命体からの視点のようなものを追い求めていたが、本作では、落ち着いた映像を通じてそれに匹敵するものを作り上げている。決定的に――そして逆説的に――自然光を用いた徹底したカメラ配置によるまっとうで苛立たしいほどバランスの取れた手法は、シナリオの極みを見事に表現している。冒頭のあるシーンで、ルドルフが子供たちに祝われるところで、彼が目隠しをして階段を降りていく様子が描かれているが、これは彼の日常の仕事の皮肉であり、一時的に目が見えないという彼の状態は、より深い現状否定を示唆している。その後、家長であるルドルフが就寝前に邸宅の中の多くのドアを几帳面に閉めて鍵をかけていく(メスを操るような素早い手さばきで用心深く、決められた手順通りに執り行われる)が、居心地の良い家庭的な雰囲気と漠然と漂う偏執狂的な感覚が混ざり合っている。
建築的面から見ても心理的面から見てもコンパートメント化(分離隔離化)は、本作におけるグレイザーのテーマをなしており、ポーランドの迷路を思わせるヘスの邸宅を細部まで緻密に再現している(その異常なまでのプロダクションデザインは、クリス・オッディの手によるもので、彼のチームが撮影前に4か月をかけて庭園エリアの設営と造園を行った)。グレイザーの脚色における構造主義的なコンセプト――その正確なテンポ、最小限の無数のリズムの繰り返し――のほとんどは、グレイザーとチームの、最大10台の固定カメラ(5人の撮影チームによって遠隔操作された)を使用して、セット内の異なる部屋でのシーンを同時に撮影するという独特の制作方法の副産物である。この撮影手法の効果は、サブリミナル的であり、かつ不気味で、―「ビッグ・ブラザー」のようなテレビのリアリティ番組を彷彿とさせる――支配と自発性の間の緊張状態を試す、親近感がありながら切り離された美学を生み出した。スタッフがいないため――撮影機材はセットの中に差し障りのないよう組み込まれていた――、俳優たちは細心の注意を払って構築されたセットを完全に自由に動くことができ、グレイザーは壁の向こう側にあるトレーラーから複数のモニターを見ていたのである。
劇中で、ナチス党員の同僚が「彼(訳注:所長のルドルフ・ヘスのこと)が持つ独特の強みは、理論を実践に変えられることだ」と主張するが、これは職業上の賛辞であると同時に、無意識ではあるが彼が最も陰湿で非人間的な人物だという非難でもある。制度的思考の一種の極端な事例としてジェノサイト(虐殺)が起きたという考え方がある。下部組織の現場の意見や混乱が、その行おうとしている目的に対しての真の考慮を妨げるのだ。理論の名のもとに頑なに実行されるものであるが、このことはこれまでさまざまな角度から検証されてきたが、グレイザー監督による本作は、慎重に目隠しを施された内側からジェノサイドを見つめ、知恵と歴史にあぐらをかくことをよしとしない。
賑やかな家族がよく来る敷地の裏を流れる川に並んで立つルドルフとヘートヴィヒは、将来のことを考えるカップルと同様だ。彼がベルリン近郊の強制収容所監察局――いわば本部――に異動することを彼女に告げたとき、彼女が世話してきた邸宅から離れることを頑なに嫌がるのは、正直な気持ちだろう。
自分たちは大きな組織の一部であるというヘスの心情は、見る者全員が共感でき、納得できるものですらある。目的――それがどんなものであっても――から目を離さないことは、他に目を向けないということを意味する。とりわけ、自分たちの夢によって生じる巻き添えの被害が明確に分かっているときは、なおさらである。ドアをスライドさせて閉めたり、物や人々をその場に閉じ込めるなど、すべてを封じ込めるショットなど、つまるところ本作は、歴史のドアが閉じることを拒む、徹底してオープンな映画である。歴史とは、危険なほど永遠に開かれたままなのである。
DIRECTOR’S INTERVIEW
――本作を監督するいきさつを教えてください。
私はそんなに多くの作品を監督しているわけではありません。何かを作るときは、完成するまでそのプロジェクトに打ち込むという傾向があります。掛け持ちをするようなことは絶対にありません。最後の映画(『アンダー・ザ・スキン 種の捕食』)を完成させたとき、本作のテーマが持ち上がりました。これは私が人生のある時点で常に挑戦しようとしていたものだったと思います。しかし原作を読むまで、この映画の視点について考えたことがありませんでした。描かれた視点の中に私に響くものがあったので、(プロデューサーの)ジェームズ・ウィルソンに電話して小説を読むよう勧めました。小説の中の強制収容所長であるパウル・ドルが物語を牽引するのですが、極めてグロテスクなキャラクターです。エイミスはアウシュビッツの実際の所長であるルドルフ・ヘスに基づいてパウル・ドルを描いたのは明らかで、私はその小説から、物語の片隅にある程度記されていたヘスと妻のヘートヴィヒについて、アウシュビッツでどのように暮らしていたかについて読み、調べ始めました。夫婦は大きな庭がある邸宅に住み、そこには強制収容所と隔てた共有の壁があった。本当に、それは私にとってある意味で壁になりました。
――この映画で、コンパートメント化(分離隔離化)が主要なテーマのように見えますが、すべてのカメラで別々の部屋を同時に撮影するという、この映画の作り方の中心でもありますね。
映画を作るにはとても奇妙な方法ですが、それが私にできる唯一の方法でした。距離を取りたかったのです。登場人物と離れたかった。触れるのが怖かったということではなく、むしろ法医学的に調べたかったのです。人類学的にと言ってもいいかもしれません。だから撮影監督と逆光や女優の髪に光が十分に当たらないことについて話し合うことをしませんでした。適切なレンズを使用しているかどうかとか、肩越しの撮影が必要かどうかなどについても。魅力的に描きたくなかったのです。それをするのが映画の常で、それは映画という言語では極めてたやすいことですから、“美化しない”というのは容易なことではありません。傍観してみたいとだけ思っていたのです。そうするとその後、プロットにも徐々に興味を失っていきました。単なるホロコーストを背景にした物語を作りたくはなかったのです。テーマをどんどん掘り下げていった。そうしていくうちに、どうやって映画を撮ればいいのか、また自分が映画にしたいものはどんなものなのかが分かってきました。
―この映画は、あなたが見ているものに関して非常に控えめです。それは、ある種の傍観者的で、不介入を通して、あるいは純粋に音を通して虐殺を描こうとしていますね。
私が撮りたかったのは、誰かがキッチンで一杯のコーヒーを注ぐ様子と、壁の向こう側で誰かが殺される様子とのコントラスト、その両極端の共存です。そういった空気感を観客はどのように受け止めるか。そこで私はこう考えました。この人たちはこの家に住んでいて、4年間にわたって罪を犯してきた。そして私は自問しました。いつ我々はメスを入れるんだ、いつ彼らのことを取り上げるのだと。
――非常に綿密な調査があったんでしょうね。脚本を書き始める前に、2年間調査しました。
映画のスタッフにはアウシュビッツ・ビルケナウ博物館の研究者にも参加してもらいました。彼らの仕事は、被害者や生存者の何千、何万もの証言である「黒い帳簿(blackooks)」をすべて調べることでした。私はルドルフ・ヘス、あるいは彼の妻や子供たちと関係のあるものを探していて、数か月後、彼らが私たちに資料、時には小さなもの、時には出版されたものを提供し始めてくれました。庭師や何人かの使用人からの証言などです。そのうちの1つに、戦争を生き延びた庭師が、ルドルフが転勤することについてヘートヴィヒが文句を言い、激怒した瞬間について語ったものがありました。彼女は夫に、当局が自分をこのアウシュビッツから追い出すことになると語っていました。これを映画の設定にしたいと考えたのです。この人事異動の時、彼女は丹精込めて作り上げたものすべてのものを失うという脅威にさらされます。我々が作った映画は、男とその妻を描いたファミリードラマです。2人は幸せに満ちている。美し
い家に5人の子供と住んでおり、妻は庭いじりに精を出し、自然に囲まれた暮らしを満喫している。夫は重要な仕事を任されており、それをそつなくこなしている。2人は申し分のないパートナー同士ですが、会社が自分を別の都市へ異動させたいと考えているという知らせを夫は受け妻はショックを受ける。一緒に行きたくないと。2人の結婚生活には亀裂が生じるが、彼は行ってしまう。夫婦はできる限りのことをして、すべてを投げ出すことはない。そしてハッピーエンドを迎える。彼は戻ってきて、仕事を続け、家族と一緒に好きなことをする。ひとつ言い忘れていたのは、彼はナチスのアウシュビッツ強制収容所の所長だということ。ここから傍観者的な虐殺というテーマが生まれたのですが、この物語はある意味で我々を描いた物語でもあることが分かります。この物語の中で自分自身の姿を見い出すか、自分自身を見ようとするかということ。我々が最も恐れているのは、自分たちが彼らになってしまうかもしれないということだと思います。彼らも人間だったのですから。
――あらゆることが整然としていることが、苛立たしいですね。映画の視線は、非常に正確で、非常に均一的で、極めて中立的な態度を取っています。
それは確かです。だがバランスというものは必要でした。ある程度の明るさも必要でした。ポーランドへ何度も行ったのですが、最初のとき、暗闇しかなかったら映画は作れないと思ったのを覚えています。90歳の、当時あの場所にいて、元パルチザンだった女性に出会いました。当時12歳だった彼女は、ポーランドのレジスタンスの一員として、組織の命令であちこちに行っていたのです。彼女は私に、外に出て何人かの収容者にこっそり食事を与えていたと言ったが、それを自慢げに言ったわけではありませんでした。そういうことが起きていたのです。彼女がしたことは、あの状況下での彼女の年齢では自然なことだったのです。自分の子供たちのこと、そして彼らの窓の外にあるものについて考えさせられました。つまり今のこの普通で健康的で幸せな環境について。少女時代の彼女の窓の外では、人々が追い詰められ、殴打され、処刑されているのが見えた。彼女は収容所から2キロほどのところに住んでいたのです。彼女の話は私の心に残り、それがとても神聖なものであるように感じた。宗教的な意味ではなくてね。でも彼女はヘスの分光のスペクトルの対極に位置していて、まぶしい光でした。映画が撮れそうな気がしました。映画で彼女は熱を表示するイメージ(サーモグラフィー)で表現されています。音楽を見つけて、演奏するのは彼女。またリンゴや梨を集めて、彼らのところに置いていくのも彼女。彼女は映画の中で非常に重要な役割を果たしていますが、実際には登場人物ではありません。私は彼女をエネルギーとして捉えたのです。
――この映画には、非常に奇妙で制御された形式的な映像がたくさんあります。サーモグラフィーについて言及されましたが、プロローグ(序幕)もコーダ(結び)も完全に黒い画面で、冒頭のタイトルが現れ、徐々に暗闇の中に消えていきます。またフィクションとドキュメンタリーのつなぎも、全くの予想外のものでした。
それはすべて、21世紀のレンズ(視点)を持ち続けることと関係しています。他のあの時代を描いた映画のように作って、それを博物館に展示するような感じにはしたくなかったのです。「あの時はこうだった」みたいなね。我々はおそらく人類史上最悪の時代について描いているのに、「それはそっとしておこう。それに我々のことじゃない。我々は安全だ。80年前の話じゃないか。もう我々には関係ない」となっている。だが、それはそうなのですが、困ったことに、常にそうなりかねないわけです。だから常に現代の目で見ていたかったのです。また我々は、すべてにおいて新鮮さを意識していました。あの邸宅はヘス一家が住む数年前に建てられたものでまだ新築と言っていい。アウシュビッツ強制収容所も新しそうに見える。今では15メートルほどの木々も、当時は苗木でした。すべては真新しいもののように見え、それをカメラに収めました。あらゆるものがくっきりとちゃんとしているのですが作者が見えない、つまり実体がないように感じる。サーモグラフィーの映像も同じところから発想しました。この映画では、撮影用の照明を全く使っていません。どれも自然光か、誰かがスイッチを入れた部屋の照明だけ。つまりリビングルームを照らしたり、野原を照らすつもりもなありませんでした。当時、夜の野原では何も見えないのです。
――複数のカメラの設定における自由度と管理の関係についてお聞かせねがえますか?
多くのシーンは、細かく管理されているというよりも、(俳優の)動きに合わせているように感じられます。これは半即興パートと綿密に計算されたマスターショット で構成されている「アンダー・ザ・スキン 種の捕食」に似ていますね。“アリーナを作る”という感じでした。この映画を監督するのは奇妙な仕事でした。カメラが何を映すかについては、かっちりと決める必要がある一方で、完全な即興のためにフレームに余地を与える必要があったからです。即興で作られたシーンもあれば、慎重に台本が書かれたシーンもあり、どちらの場合でも、いつでも別テイクができるわけですが、セットの中に私が入っていき椅子を動かすようなことはしませんでした。そうすると連続性が失われる。照明もなくしました。ある意味でマイクロマネジメント(細かいところまで目を配って演出する)を手放す必要がありました。私は座って10台のモニターを見ているだけですから。映画の中で、ヘートヴィヒが友人たちとコーヒーを飲んでいるシーンがありますが、ルドルフは彼のオフィスで、新しい火葬場のデザインを売り込みにきた建築会社のトップフ・ウント・ゼーネ の重役たちと一緒にいて、親衛隊の将校たちが誕生日のお祝いのためにやって来て、メイドたちが行ったり来たりしている。これがすべて同時に起こり、私の話せない言語で撮影されている。まさに狂気の世界なのですが、それと同時に他の撮影方法では得られない、すべてのシーンで均一なトーンで撮れることは分かっていました。
――“アリーナ”というのは非常にうまい比喩ですね。空間には非常に緊張感があり、観客はその境界を把握するために多くの時間を費やします。ルドルフがドアを閉めて、電気を消して、歩き回るシーンには構造主義的な部分が垣間見え、非常にドメスティックですが、非常に不気味で儀式的でもあり、どのカットも非常に正確です。
まるで映画の中の小さな映画のようですね。だが私は彼をとても怖がりだと思っていて、あのシーンはその恐怖の一例です。彼が何を気にかけているのか、そして私たちが誰を気にかけているのか、どの肉体(人間)を気にかけていて、どの肉体(人間)を気にかけていないのかを考えさせられます。
――映画の後半で、少なくともドアの1つは双方向に開く可能性があり、ある意味で彼はアウシュビッツの壁の反対側に住んでいないことに観客は気づきます。彼は家から出ずに(収容所に)入る方法を知っていますが、それは恐ろしいことであり、同時に現実的でもあります。彼は実際に仕事を離れることはありませんし、家を離れることもありませんね。
あのトンネルは本当にあったのです。彼が使う浴室は実際に地下室にありました。とても奇妙で、とても不気味なのですが、すべてが非常にグロテスクに設計されていたのです。どんな些細なところまでも。
――この映画には、見た目にも比喩的にも、“壁の向こう”をのぞいたり、壁を越えたりする潜在的なチャンスがあることを考えると、暴力を見せることを絶対にしないという選択について話してもらえますか?
ホロコーストの表現の倫理に関するミーティングから生まれたものです。表現の倫理に関する物は、数多く読読みました。どのようしてホロコーストを見せるのか?または見せないのか。すべてを描くのか、それとも部分的に描くのか? 私は暴力の再現はしたくないと思っていました。縞模様のパジャマを着たエキストラが殴られるのは見たくなかったのです。たとえ殴られるふりがうまく演じられたとしても…。そしてエキストラは(その格好のままで)ケータリングテントの中でアップルカスタードを食べるわけですからね。私は早い段階でそのことに危機感を抱き、その後、ますます胸が締め付けられるようになりました。初期の草案にはいくつかの暴力的なシーンが含まれていましたがそれらは消えました。私が決意を撤回した場合に、ホラーとして扱われたりするなどの起こり得る恐ろしい結果について考えました。私としては、その一翼を担いたくなかったのです。音、その音に対する解釈を、私たちが学校で見たり、勉強した映像が埋めているということを考えました。映像を見せていませんが、それらの映像は映画のすべてのフレーム、すべてのピクセルに反映されていると思います。
――映画の壁を突き破りそうになったものはありましたか?
ノーとは言いません。確かに壁を突き破るようなものを書いたが、それを撮影することはありませんでした。いいですか、我々はアウシュヴィッツの土の上にいたのです。ドイツ人俳優たちは、自分たちの祖父母である可能性のある人々を演じるために来ていました。とても不思議な雰囲気だった。それが映画の現場で、あるいはその国の他の場所でも作り得たかは分かりません。一緒にいた人たちに、あれはこの場所だったと話したことを覚えています。まさに、その場所だったのです。
――ある時点で、ヘートヴィヒは母親に「ユダヤ人は壁の向こうにいる」と言います。それは事実なのですが、その言葉の裏には信じられないほどの現状否定と抑圧の感情が潜んでいますね。
ハンナ・アーレントがジェノサイドの思慮のなさについて語っています。それは上品にも思えるし、不適切なようにも見えますが、彼女はある意味、文字通りの意味で言っています。「何も考えていなかった」と。あるとき、(ヘートヴィヒ役の)ザンドラ・ヒュラーが私の元にやって来た。ヘス一家が自分たちの将来について話す川岸のシーンの撮影の前のことです。ヘートヴィヒの心は動くのかと聞いてきた。私は「もちろん、そうだ」と言った。彼女は人間だ。問題は彼女の心が動いたかではなくて、何が彼女の心を動かしたかだ。彼女は何に動かされているのだろうか?だから、このシーンで泣くなら自分のためにだけ泣いてほしいとね。彼女(ヘートヴィヒ)とルドルフがベッドで横になっている別のシーンがあります。間取り図は正確に再現していてベッドは別々。2人の会話がおぞましいのです。彼女はスパに戻りたいと思っているが、彼は転勤のことを考えている。彼女は笑いながら横になっているんだが、我々はそれをモニターで見ていた。笑いというのは伝染すると知っていますか?我々は彼らの側に立っているのだろうかと思った。我々は彼らに共感しているのか?ここで何をしているのだ?って。
――夫婦は夢を追っています。家を建て、土地を耕し、この国家主義的なイデオロギーを実現しようとしています。“明日は自分たちのものだ”と思って。…。
一歩一歩。彼らはありのままを表現しました。彼らはアメリカンドリームに触発されていたのです。ドイツ人にとって「東へ行く」は(アメリカ人の)「西へ行く」と同じようなものだった。“大地を駈け巡れ”と同じ気持ちだよ。それが人間というものだよ。
――映画の後半で、ルドルフが仕事に向かう途中で吐く非常に重要な瞬間があります。まるで彼の体が自分のやっていることに疑問を抱いているような感じです。すると突然、私たちは現在のアウシュビッツに飛びます。観客は過去の世界から脱却しますね。
私はそれが過去から現在に向かうものだとは考えていません。私はそれを未来の今として捉えています。すごく不思議なのですが、初めてあの場所を訪れた後、脚本に「今のここ」と「あの頃のあそこ」を紡ぐという一文を入れました。自分へのメモでした。彼は任務を続け、とにかくそれを実行する。彼は帽子をかぶり、階段を跳ね降りて仕事を続ける。そして次の瞬間、未来を見て、彼は自分が引き起こした惨状の目撃者となるのか?彼はそれを想像しているのか?彼はお構いなしに続ける。私たちは関係なく続ける。誰に対しても二度としないのか、それとも私たちに対しても二度としないのか?それは私たちが黙許しているものです。
――彼の吐き気は無意識なものであるため、このシーンは強烈です。彼はそれについて何の感情も示しませんが、とにかく吐き気を催します。抑えられないわけですね。
ホロコーストについて多くの著作を残した優れた哲学者ジリアン・ローズは、自分が思っている以上に我々が加害文化に感情的、政治的にどのように近づいているかを示すことで、私たちに“安全ではないこと”を感じさせる映画を構想しました。それは、彼女が言うところの“深い悲しみの乾いた目(ドライアイ)”が私たちの心に残すかもしれないものです。ドライアイと感傷的な涙。これは本当に強烈なアイデアだと思いました。そしてそれこそ私が挑んでいる映画だ。それは冷たい映画ではなく、法医学的な映画でなければならないと思いました。
-726x1024.jpg)